
#AKさんさん色彩検定をいきなり2級から受けるのってありなのかな?

結論から言うと、色彩検定はいきなり2級からの受験が断然おすすめです。
詳しく解説するね!
「色彩検定、いきなり2級から受けていいのかな?」
「まずは3級から?…でもそれって遠回り?」
そんなふうに迷っているあなたへ。この記事は、色彩検定を効率よく、そして自信を持って合格したい人のための“上質な参考書”のような存在になれるように書きました。
結論から言うと、色彩検定はいきなり2級からの受験が断然おすすめです。私自身は3級から受験して合格しましたが、今振り返るといきなり2級でよかったなと心から思います。
なぜなら──
- 試験回数を減らせて、時間とお金のコストを節約できる
- 2級の勉強を進めるうちに、自然と3級の知識も身につく
- そもそも3級は難易度がそこまで高くない
この3つの理由から、いきなり2級からのチャレンジを私は強くおすすめします。
この記事では、
- 色彩検定はいきなり2級から受けた方がいい理由
- 最短で2級に合格するための学習法
- それでも3級から始めた方がいい人の特徴
を、私自身の体験もまじえて、分かりやすくご紹介します。
まずは、「これは間違いない」と思える上質の参考書を手に取ることから、すべてが始まります。
いきなり2級はハードルが高いと思われがちですが、色彩検定は出題範囲が明確で“勉強すれば確実に点が取れる”検定です。
だからこそ、いきなり2級を目指す方には、公式テキストと過去問題集を使った対策がもっとも効果的となります。
▼ 私が実際に使って、本当に頼りになった参考書はこちら↓
色彩検定をいきなり2級から受ける前に知っておきたい基礎知識

まずはじめに、色彩検定をいきなり2級から受ける前に最低限知っておきたい基礎知識を紹介します。
色彩検定とは?
色彩検定(しきさいけんてい)とは、公益社団法人色彩検定協会(旧・社団法人全国服飾教育者連合会(略称はA・F・T))が実施する色に関する知識や技能を問う試験であり、1級から3級までの3段階に分かれている。
平成2年(1990年)11月に「ファッションカラーコーディネーター検定試験」として始まり、「ファッションコーディネート色彩能力検定」と名称を変更した後、2006年度からは「色彩検定®」として実施されている。
1995年度から2005年度までは文部科学省認定の試験であったが、認定制度の廃止に伴い、2006年度からは文部科学省後援の試験となった。色彩に関する試験としては最も歴史がある。
合格すると色彩検定協会により色彩コーディネーターの称号が与えられる。主催団体の前身が服飾系の団体であったため、試験内容や取得に向いている層もファッション・アパレル系といわれているが、現在ではそのようなことは無く、色彩に関する基礎や配色技術、その他幅広い知識(インテリア・環境色彩・カラーユニバーサルデザイン等)を学習できるものとなっている。
参考にしたのはこちらの記事:色彩検定公式ホームページ
いきなり2級から受験しても大丈夫?
色彩検定は、いきなり2級から受験することが可能です。
当然ながら3級の内容も含まれるため、相当の知識が必要となります。
合格できる確率はどれくらい?
色彩検定2級の合格率は、毎年7割前後の合格率となっており、2024年度の合格率は69.1%。また、3級と2級の合格率にはわずか約5%の差しかありませんが、2級と1級の合格率には約27%もの開きがある。
2024年度 受検状況
| 区分 | 志願者(人) | 合格率(%) |
| 1級 | 2,456 | 41.8 |
| 2級 | 15,308 | 69.1 |
| 3級 | 27,192 | 74.7 |
| UC級 | 4,406 | 78.7 |
| 合計 | 49,362 | – |
色彩検定いきなり1級を受けるのは難易度が高いですが、いきなり2級を受ける場合は難易度がそこまで低くないことがわかります。
合格までに必要な学習時間
次は各級において必要な学習期間の目安を一覧にした表です。
2級に必要な学習期間は2ヵ月間となります。これは、3級の知識がある事前提としての期間となります。また、3級に合格するために必要な期間は1ヵ月程度が目安。そのため、いきなり2級に合格するには、3ヵ月程度は学習期間が必要なことがわかります。
| 区分 | 必要学習時間 | 注意点 |
| 3級 | 1ヵ月程度 | |
| 2級 | 2ヵ月程度 | 3級の知識がある事前提として期間 |
| 1級 | 2~3ヵ月程度 | 合計150時間(1日2時間だと75日、1日3時間だと50日) |
色彩検定の試験日・申込スケジュールは?
2級は夏期と冬期の年2回試験が開催。そのため、いきなり2級に挑戦するには年2回のチャンスがあります。
| 区分 | 試験回数 |
| 2級・3級 | 夏期と冬期の年2回 |
| 1級 | 冬季に1回 |
応募スケジュールイメージ
検定の応募は夏期、冬季ともに約2ヵ月前から受け付けています。
| 区分 | 試験日 | 申込期間 |
| 夏期検定 | 6月22日(日) | 4月1日(火)~5月15日(木) |
| 冬季検定 | 11月9日(日) | 8月4日(月)~10月2日(木) |
色彩検定をいきなり2級から挑戦するには試験日から約2ヵ月前に申し込みが必要です。
色彩検定はなぜ「いきなり2級」からの受験がおすすめなのか?

なぜ色彩検定はいきなり2級からの受験がおすすめなのか。
それは、私自身が3級から順番に受験した経験から、「最初から2級を受けておけばよかった」と強く感じたからです。
今から色彩検定を目指す方には、ぜひ「いきなり2級」という選択肢を真剣に検討してみてほしいと思います。
その理由は、以下の3つに集約されます。
1.試験回数を減らせて、時間とお金のコストを節約できる
2.2級の勉強を進めるうちに、自然と3級の知識も身につく
3.そもそも3級は難易度がそこまで高くない
それぞれの理由について、丁寧にわかりやすく解説していきます。
試験回数を減らせて、時間とお金のコストを節約できる
いきなり2級から受験することで、色彩検定にかかる費用と時間の無駄を最小限に抑えることができます。
色彩検定を3級から受けてしまうと、当然ながら2回分の受験料がかかります。2025年現在、3級の受験料は7,000円、2級は10,000円なので、順番に受けると合計で17,000円かかります。対していきなり2級なら10,000円で済むため、7,000円の節約に。
さらに、試験の申し込み手続きや当日の移動・拘束時間も2回分必要になります。特に試験当日は、指定された会場に赴く必要があり、準備や移動時間も含めて半日以上がつぶれてしまうケースが多いです。これを時給換算すれば、時間的コストも大きな負担となります。
つまり「いきなり2級」を選べば、金銭面と時間面、どちらの観点でも非常に合理的な選択になるわけです。
2級の勉強を進めるうちに、自然と3級の知識も身につく
色彩検定2級の学習内容は、3級の内容を含んでいるため、あえて3級から始めなくても、2級の勉強を通して自然と3級レベルの知識を習得できます。
2級を勉強するうちに3級の知識も身につく上、紐づけて覚えていくことが可能なので、いきなり2級を受ける方が効率が良いと感じました。
逆に、3級合格から2級受験までに期間が空いてしまうと、せっかく覚えた内容を忘れてしまうことも。例えば、冬期に3級を受験し、次の夏期に2級を受ける場合、約半年間のブランクが生まれます。2級の学習に必要な期間は約2ヶ月とされているため、残りの4ヶ月は知識の風化リスクにさらされることになります。
このようなリスクを避ける意味でも、いきなり2級は非常に有効な戦略です。
効率的に学習を進めたいなら、最初から2級を目指す「いきなり2級」がおすすめです。
そもそも3級は難易度がそこまで高くない
色彩検定3級は、基礎的な内容が中心で難易度が低めなため、2級から挑戦しても問題なく対応できます。
色彩検定3級では、「色とは何か」といった基礎知識や日常生活でもよく耳にする色彩理論が中心です。内容自体も比較的やさしく、暗記量も多すぎないため、初学者でも取り組みやすいレベルとなっています。
そのため、「3級からじゃないと不安…」という気持ちがあっても、2級の勉強に取り組んでいれば、必要な基礎は自然と身につけられます。実際に私も、「3級は不要だったな」と感じるほど、2級の学習の中でカバーできる範囲でした。
いきなり2級というアプローチに不安を感じている方でも、3級の内容が自然と吸収できるとわかれば、安心して一歩を踏み出せるのではないでしょうか。
まとめ
このように、いきなり2級は費用・時間・学習効率のすべてにおいて非常にバランスの良い選択肢です。色彩検定を検討している方は、ぜひいきなり2級という選択肢を視野に入れてみてください。
「色彩検定って、本当に取る価値あるの?」と思っている方へ。私が実際に受けて感じたメリットはこちらの記事で詳しく解説しています。
→ 色彩検定のメリットとは?キャリア成長に役立つ理由を合格者の実体験から徹底解説!
色彩検定2級に私はこうして合格!【いきなり2級にも通用するリアル体験談】
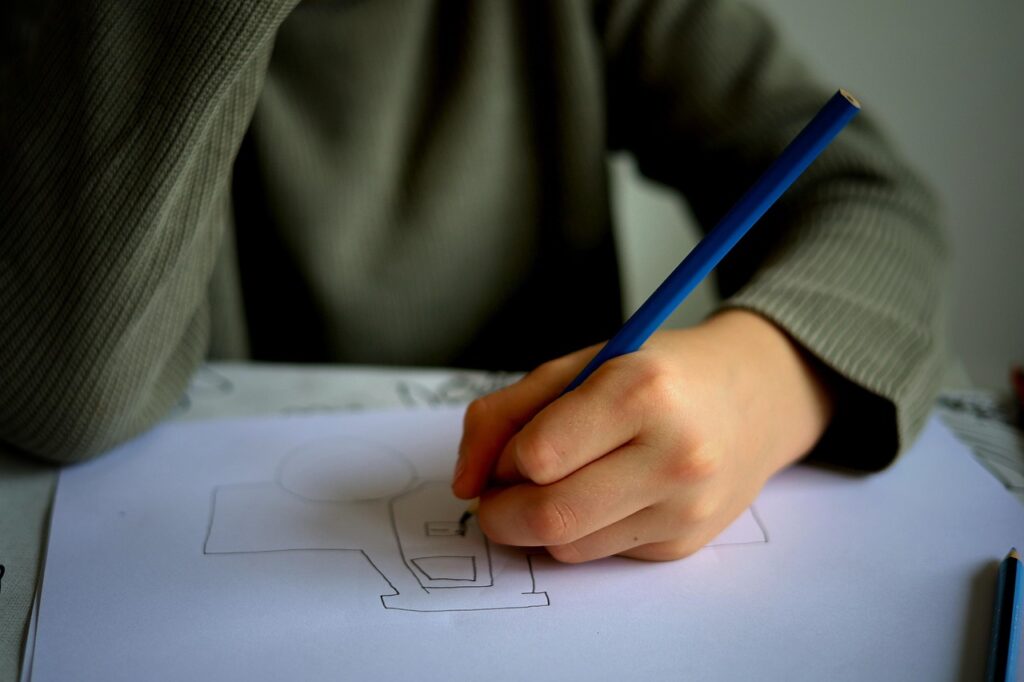
ここからは私が私がいきなり3級合格、そして2級もいきなり一発で合格した学習方法を解説します。自分に合った勉強法を見つけ、いきなり2級合格を目指しましょう。
2級合格までにかけた学習時間の目安
・【学習期間:12週間】目標と試験日から逆算して計画を立てた
まず初めに私は学習期間をしっかりたてました。必要学習時間が150時間と設定されているため、1日3時間捻出できるとしたら、約50日間必要な計算となります。一方で勉強できない日も発生することを見越して必要な学習時間は60日間として若干猶予を持たせた計画をたてました。
私は仕事をしながら学習を勧めたので、出社前に3時間確保して勉強しました。
終わらなかったら、可能な限り夜にこぼれた分は終わらせるようにしました。それでも終わらない場合は、日曜日をバッファとして用意していたのでそこで回収するという2段構えで対策しました。
いきなり2級を狙うなら、毎日のスキマ時間をどう確保するかがカギになります。
・【学習時間:150時間】「何分やるか」より「どこまでやるか」が大切
特に気を付けたことは、時間をきめて勉強を進めると、10個覚えたかったことが5個で終わっても満足してしまう懸念があったため、どこまでやるかを大切にしました。一方でその日どこまでやるべきかきまっているので、翌日の学習時間に影響が出ないように頑張りすぎず、その日やるべきことが終わったあとは意識してのんびりすごしていました。
このやり方は、いきなり2級を目指す人にもおすすめの進め方です。
色彩検定2級合格のために実践した勉強法|準備編
・まずは公式テキスト&問題集を揃える
まずは公式テキストと問題集を買いそろえることが最初の一歩です。色彩検定は出題範囲や傾向がシンプルなため公式のものが最も適切でした。私が使ったのは以下のテキストです、まずは雰囲気を知る為に購入をおすすめします。
・その他の教材は必要?
その他の教材に関しては基本的に不要でした。正直な所問題集が一冊増えるたびに解かなければいけない問題数が一冊分増えてしまうので、学習効率としては低いと感じます。かわりに、公式テキストを何度も繰り返して百点になるまで説き続けることを意識します。
いきなり2級合格を目指すなら、教材の数を増やすよりも繰り返し解くことが重要です。
・学習スケジュールをしっかり立てる
実は私は最初の数週間は無駄に過ごしてしまいました、学習計画を立てずだらだらとやってしまったからです。計画を立てないとものすごく進みが良い日もあれば、あまり進まない日もあり、結果的に進みが悪い日が多くなりました。
とくにいきなり2級を目指す場合、無駄な時間が合格を遠ざける原因になってしまいます。
色彩検定2級合格のために実践した勉強法|実践編
私がもっとも重要視したのは、出題傾向を確認し学習ボリュームを最低限に下げることです。次に学習のフェーズを三段階に分けました。理解→インプット→アウトプットの工程です。
理解の段階では知ることに重点をおき、インプットの段階では理解しきれなかったところをさらに丁寧に読み込んでゆき、アウトプットでは知識を外に出せるように過去問をほとんど完璧になるまで繰り返し説き続けました。
この方法で3級もいきなり2級も一発で合格できたので、最も良い学習方法だといえます。
この三つのフェーズを細かく刻むと次の学習フローで、具体的に解説すると以下となります。
・まずは過去問に触れて出題傾向をつかむ
まずは、過去問を1回本番の試験時間で試してみましょう。
もし、終わらなかったら試験時間を超えても最後までやってみます。この段階で色彩検定が文字を書くタイプの試験なのか、選択問題なのかを把握します。
その他にも気づいたことがあればメモしています。私は、このタイミングで色彩検定はマークシートだということがわかったので漢字をかけるようになる必要はなく、読み方にもあまりフォーカスせず一つ一つの単語を理解することに重心を置く勉強法にしました。
もちろん一定の記憶は必要ですが、これにより学習時間を大幅に削減できたと感じています。また、いきなり2級合格を目指す人にとっても、まずは過去問で全体像をつかむことが重要です。
・テキストを順に読み込み、ノートで整理する
出題傾向が理解できたところで、テキストを丁寧に読んでいき、全体像を把握します。記憶物をいれる箱を用意していくイメージです。
ざっくりと目次を理解してその中にどのような知識が必要なのかを分類してメモ。基本的には目次を写し取っていくようなイメージです。
いきなり2級を受験する場合でも、目次構造の理解と項目の整理は大きな武器になります。
・全体の出題範囲を俯瞰してイメージを持つ
全体のおおまかなテキスト内容を自分なりに整理し終わったところで、各項目の中に記憶しなければいけない用語をすべて書き出していきます。
このタイミングでもどんどん頭の中に入っているのでめげずに頑張りましょう。そして、まとめ終わったらそれらを俯瞰します。
これにより記憶するボリュームがどれくらいあるのかを把握します。このタイミングで初めて記憶しなければならないボリュームが明確化されたので、改めて毎週どこまで記憶すればいいのかを確認し、計画に問題がないかを再確認します。
このあとは記憶のフェーズに入りますが、この段階である程度理解が終わっているのですでに本番の問題も3割から4割は正解できるはずです。
・理解した内容をしっかり暗記
ここからは、しっかり暗記を行っていきます。
書き出したメモ帳で覚えておいた方がよさそうな所に赤線を引いて、なんども繰り返して記憶していきます。有名なエビングハウス忘却曲線では、誰しもが一時間後には記憶したこと44%を忘れてしまうとあります。
基本的にこの割合で覚えたことを忘れてしまうので、定期的に記憶作業を繰り返し記憶を定着させていきます。だいたい3回目から5回目には記憶が定着します。
いきなり2級を狙うなら、忘却を見越した記憶戦略はマストです。
・再度、過去問や問題集を解いて弱点を洗い出す
ここからはアウトプットのフェーズに入ります。再度過去問や問題集を解いていきます。
このタイミングでは正答率5割前後になっていればOKです。何度も過去問や問題集をといて百点になるまで繰り返します。また、違う言い回しで質問されても答えられるように不安を感じた部分は改めて学習テキストを読んで理解します。
3回くらい問題集を繰り返したころには合格点をとれるようになっているはずです。問題が出た時に記憶から取り出せるようになることが常陽なので、間違えても2秒以内に次の問題を解き進めます。
いきなり2級を突破したい方は、アウトプットにこそ時間をかけるべきです。
・間違えた問題は答えを徹底的に覚え直す
試験直前はどうしても覚えられないことが残って行きます。最後はここにだけフォーカスを当てて記憶して行きます。
しかし、私はどうしても覚えられないことが試験直前に残ってしまう人間のため、最後はA4用紙にどうしても覚えきれなかったことを書いておき、試験の本番着実に読んで試験中に回答できるように対策しました。オススメの方法です。
以上が私がいきなり3級合格、そして2級もいきなり一発で合格した学習方法です。自分に合った勉強法を見つけ、最短で合格を目指しましょう。
私絵師になる為に色彩検定にチャンレンジしましたが、自身も色彩に関しては最初はまったくの素人でした。そんな私が一歩踏み出したきっかけは、【ある転機】にありました。
▶私が絵師になると決めた日|“挫折”からの転機とは
こんな人は色彩検定は3級から受けるのがおすすめ

学習に使える時間が限られている
試験の応募期間は試験日に対して3カ月前が目安です。応募のタイミングを考えると日数に関して言えば充分な学習期間が取れると判断できます。一方で学習時間の中で一定の期間は仕事に集中しなければいけないなど、学習時間が間引かれてしまう方はギリギリのタイミングとなる方もいるかと思います。その場合はいきなり2級を狙うよりも、まず3級を受けておき次回の2級に備える対策をオススメします。
2級で落ちたときのメンタルダメージが不安な人
私がかつてSEO検定を受けた時のことです。この資格は1~4級までありこの時に発生したのですが、1~3級を飛ばしていきなり1級を受けた時のことです。あと2点で合格というラインで1級に落ちてしまったのですが、
再受験するときに自分は2~4級に関して、どの程度自分は合格ラインに届く力が培われているのか判断できずというか不安になってしまい。膨大な範囲を再学習しなければならない状況に陥ったことがあります。
色彩検定でもいきなり2級を受けて同じ状況に陥る方は少なくありません。自分の記憶できている範囲を正確に把握できる方は問題ありませんが、その点に不安を感じる方はいきなり2級を避け、3級からの受験がおすすめです。
3級までの資格で十分という目的の人
自分が本当に2級が必要か再確認することも重要です。とりあえず3級までの資格だけあればいいという人は、万が一いきなり2級を受けて落ちてしまった場合、知識は残らないので、文字としての実績が残らない状態になってしまうので注意が必要です。また、いきなり2級を受ける場合は、それなりに時間と集中力を投資する覚悟が必要だという点も忘れずに。
いきなり3級からチャレンジしたい方はこちら↓
また、いきなり2級からチャレンジする方も3級のテキスト購入が必須!
色彩検定を通してスキルを身につけた後、「この資格を仕事に活かしたい」と考える人も少なくありません。
実は私自身も、転職を経験しました。資格が自信になり、次の一歩を踏み出す後押しにもなったのです。
▶転職する気なんてなかった40歳の私が、エージェントに登録した理由
まとめ:色彩検定は「いきなり2級」から挑戦するのがおすすめ!
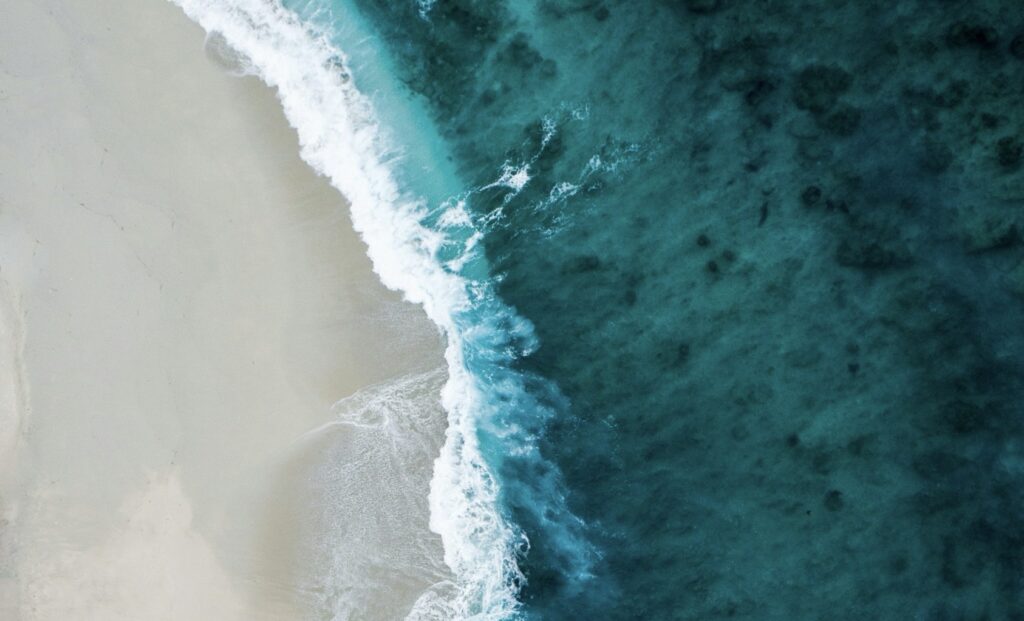
色彩検定はいきなり2級から挑戦するのがオススメです。いきなり2級に挑戦するときポイントは、
- テキストは公式テキストをしっかりやりこむ
- 学習計画をしっかり立てる
- 勉強するときはバッファを設ける
です。
いきなり2級はハードルが高いと思われがちですが、色彩検定は出題範囲が明確で“勉強すれば確実に点が取れる”検定です。
だからこそ、いきなり2級を目指す方には、公式テキストと過去問題集を使った対策がもっとも効果的となります。
▼ 私が実際に使って、本当に頼りになった参考書はこちら↓






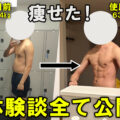

コメント